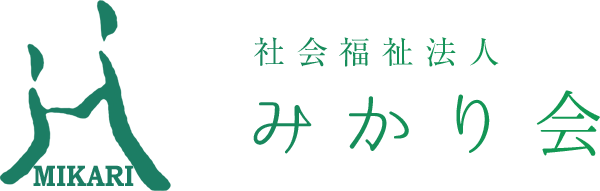事業計画
研修委員会 COMMITTEE

職員も講師に

和やかな研修会風景
経営方針
■「論理の展開」を体験し、知性(認知能力)を高めよう |
■知性を高めるための方法は、「論理の展開」です。教わるより、教える方が身につくのです。教わることは「学習」で、教えることは「勉強」だとも言われます。様々な立場を経験しながら、論理的思考を培い、技術を磨き、意欲を継続しながら新しいものを創造していこう |
|---|---|
■多様な関わりの中で「成功」と「失敗」を体験し、感性(非認知能力)を培おう |
■感性とは価値あるものに気づく心の感受力であり、個性の原点です。それは,多様な関わりの中での体験によって培われます。様々な体験の中で、感受力を高め、コミュニケーションスキル、リーダーシップ、公共心、規範意識、他者理解力、忍耐力などを培い、自身の個性を確立していこう |
経営目標(中・長期ビジョン)
1.専門知識・技術を高める |
より良いサービスの提供を目的に、関係する質の高い知識と技術を培います |
|---|---|
2.創造力を培う |
多様な経験と知識を得、思考、想像力を生かし新しいものをつくる力を培います |
3.論理的思考を培う |
情報収集力、問題発見力、分析力、理解力、観察力など、論理的思考を培います |
4.継続性を培う |
好奇心、探究心など、知識欲をもって、知識や能力を継続的に高めていきます |
5.コミュニケーションスキルを培う |
言語能力、表現力を高め、コミュニケーションスキルを培います |
6.リーダーシップを培う |
想像力、状況理解力、判断力を養い、柔軟性、協調性をもって対人影響力を高めます |
7.公共心を培う |
人間としての基礎・基本を土台とし、社会の一員として公共心を培います |
8.ルール・規範意識を高める |
ルール・規範的意識、倫理観、道徳性を高め、責任のある行動をします |
委員長の言葉
みかり会では、「認める」「任せる」を人財育成の基本としています。
法人内研修等で職員が講師の役割を担ったり、教育保育について語ったりすることで、「認める」「任せる」の機会となっていると考えています。
様々な体験により、教わる側はもちろん、教える側の成長につながっています。
個々の成長に応じた研修内容やシステム等の見直しも行っています。
委員長 小林 峰子
令和五年度 事業計画
- フィードバック・パワーアップ研修の階層別テーマを検討する(年2回)
- 新任研修(OJT)にて、養護面(人権擁護)について振り返りの機会を設ける(年2回)
- 非正規職員採用時マニュアル(人材育成)の活用(年1回(採用時))
令和四年度 事業計画
- 新任研修(OJT)にて、養護面の指導をする
- フィードパック・パワーアップ研修の階層別テーマを検討する
- 非正規職員の学びの場への参加を促す
令和三年度 事業計画
- 個別研修計画を簡素化し、円滑に運用できる個別研修システムを確立する
- 非正規職員採用時マニュアルを作成する
- 法人特別研修を企画、運営する
令和二年度 事業計画
- 個別研修システムの構築(自己評価チェック、個別研修計画の見直し)
- 非正規研修、新人研修、特別研修、パワーアップ研修等の企画運営
- 採用時マニュアルの作成・改善
人財確保・定着委員会 HUMAN RESOURCES

チームで頑張る
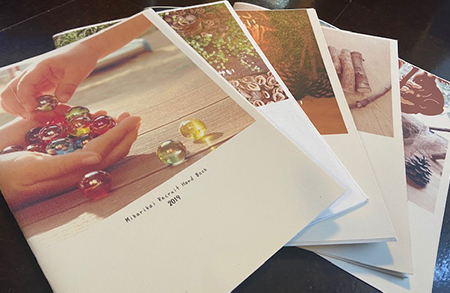
就職フェアのパンフレットも工夫して
経営方針
■学習と成長の仕組みを構築し、組織を活性化させよう |
■多様な関わりによって人は成長します。子どもも大人も同じです。私達は、他の業種にない恵まれた環境にあります。意識をしないと気づかぬほど日常的なことですが、そのことに感謝し、利用者、また、スタッフ同士などの多様な関わりの中で、立場を経験しながら、幸せに生きるためのフィロソフィ(哲学)を自ら確立していこう。 |
|---|---|
■多様な関わりの中で「成功」と「失敗」を体験し、感性(非認知能力)を培おう |
■感性とは価値あるものに気づく心の感受力であり、個性の原点です。それは,多様な関わりの中での体験によって培われます。様々な体験の中で、感受力を高め、コミュニケーションスキル、リーダーシップ、公共心、規範意識、他者理解力、忍耐力などを培い、自身の個性を確立していこう |
経営目標(中・長期ビジョン)
13.良質な人材を確保する |
様々な効果的な手段を講じ、良質な福祉人材を確保します |
|---|---|
14.上司、部下、スタッフ同士の関わりの充実 |
日常の上司、部下、スタッフ同士の関わりの中で成長できるよう健全な組織風土を確立します |
委員長の言葉
我々みかり会職員は一人ひとりが社会を構成していくために、必要不可欠な存在です。その意識と自覚を持ち、我々のミッションを共に達成していくために人財確保・定着委員会としての取り組みを進めていきたいと考えています。
まさに人財は「確保」と「定着」の両輪で動いていきます。みかり会が常に魅力的でいれるように、職員一人ひとりが主体的に物事に取り組みながら、自分自身がみかり会の「顔」であると発信していけるような集団作りを意識していきます。
委員長 藤原 剛
令和五年度 事業計画
- ツアー参加者への、その後のつながりを意識した案内の配布(年2回)
- 定期的なレクリエーション活動の実施(年2回)
- サポーティング制度にて、相談できる機会を設ける(新任職員1人に対して、年4回)
令和四年度 事業計画
- 学校訪問の実施
- 参加者・主催者側担当者へ向けた満足度調査の実施
- アフターコロナ禍におけるレクリエーション及び、余暇活動の検討を行う
令和三年度 事業計画
- 目的、必要とする人材(ターゲット)を把握した上で、必要な情報を発信する
- コロナ禍におけるレクリエーション及び余暇活動の検討を行う
令和二年度 事業計画
- 同期同士で学びを深める研修の企画・運営
- 効果的な人財確保の為の見える化・発信力の強化、強み弱みの整理
- 人財定着を目的としたレクリエーション活動の企画・運営
質の向上委員会(乳児) IMPROVE QUALITY

一人一人の養護を考える

五感で感じる
経営方針
■自分の能力を精一杯使い、子ども・高齢者・障害者、保護者の方々にお返しをしよう |
■受容的環境を確立し、ご利用いただいているすべての方が「自分らしく主体として生きること」ができるサービスを提供する真のプロを目指そう |
|---|
経営目標(中・長期ビジョン)
20.受容的環境の確立 |
人的、物的両面において受容的環境を確立します |
|---|---|
21.「自分らしく主体として生きること」を目指す保育・介護・障害福祉サービスの提供 |
「真のプロ」を目標とします |
22.「将来」へつなぐ保育・介護・障害福祉サービスの提供 |
きめ細やかに個別のニーズに対応し、アフターケアの充実を図ります |
委員長の言葉
「養護と教育」の視点を大切にしながら、こども一人一人と丁寧に関わり、受容的・応答的な教育・保育の質の向上に努めていきます。
さまざまな素材に出会い、経験を重ね、こどもたちの「不思議だな」「ワクワクする」「もっと知りたい」「やってみたい」と言う気持ちに気づき、実践し、委員会の中で共有していきます。
また、こどもの姿から環境を整備し、こどもの興味を手に取れる場に広げ、主体的な活動へと広げていきたいと思います。
委員長 林 真咲
令和五年度 事業計画
- 「こどもの人権」について委員会で検討・共有を行う(年2回以上)
- 職員の深い学びの実現に向け、施設や職員に合わせた施設評価事業を各施設にて開催(各施設年1回)
- インスタグラムを活用し、保護者や地域に向けて取り組みの発信を行なう(各施設月2回以上)
令和四年度 事業計画
- 養護、教育の視点から、バイブルブックを活用し園内研修を行う
- Tomorrow Challegeを通し、各園の質の向上へつなげる
- 子どもの姿から環境を整え、ドキュメンテーション・ポートフォリオを通し、保護者・地域へ発信する
令和三年度 事業計画
- 各施設で年3回以上、バイブルブックを活用し養護についての園内研修を行う
- 幼児の養護についての実態を調査し、養護と教育のバイブルブックを作成する
- 具体的な課題に沿った取り組み内容を実施。主には現場での対人問題。技術と意識の両面からアプローチを行う
令和二年度 事業計画
- 『養護』について継続して話し合いの場を持っていく
- マニュアルの整備を行う
- プロジェクト保育、環境について継続して探究を行う
- 教育・保育の見える化について継続して探究を行う
- Tomorrow Challenge(内部評価事業)の実施
質の向上委員会(幼児) IMPROVE QUALITY

「やってみたい」の思いが溢れて…

木工エリアの一場面 皆で力をあわせて
経営方針
■自分の能力を精一杯使い、子ども・高齢者・障害者、保護者の方々にお返しをしよう |
■受容的環境を確立し、ご利用いただいているすべての方が「自分らしく主体として生きること」ができるサービスを提供する真のプロを目指そう |
|---|
経営目標(中・長期ビジョン)
20.受容的環境の確立 |
人的、物的両面において受容的環境を確立します |
|---|---|
21.「自分らしく主体として生きること」を目指す保育・介護・障害福祉サービスの提供 |
「真のプロ」を目標とします |
22.「将来」へつなぐ保育・介護・障害福祉サービスの提供 |
きめ細やかに個別のニーズに対応し、アフターケアの充実を図ります |
委員長の言葉
主体的・対話的で深い学びを目指して、こどもにとって自由に探究し、学び合える楽しい環境を創り続けていく為に、それぞれの施設が意見を交わしながら質向上に向けて取り組んでいます。今年度も学力の三要素(知識・技能の基礎、思考力・判断力・表現力・主体性・多様性・協働性)を培う為に、養護を土台としたプロジェクト保育の展開を法人全体で検討し、より質の高い教育・保育を目指していきます。また、保護者や地域から十分な理解が得られるよう「教育・保育の見える化、魅せる化」に努めていきます。
委員長 佐々木 唯子
令和五年度 事業計画
- 「こどもの人権」について委員会で検討・共有を行う(年2回以上)
- 職員の深い学びの実現に向け、施設や職員に合わせた施設評価事業を各施設にて開催(各施設年1回)
- インスタグラムを活用し、保護者や地域に向けて取り組みの発信を行なう(各施設月2回以上)
令和四年度 事業計画
- 各施設で年3回以上、バイブルブックを活用し「養護と教育」についての園内研修を行う
- SNSを活用し、保護者や地域に向けて取り組みの見える化を行う
- Tomorrow Challegeの反省を活かして実施方法を再検討し、より質の向上へと繋げられるよう、3年間で方法を確立する
令和三年度 事業計画
- 各施設で年3回以上、バイブルブックを活用し養護についての園内研修を行う
- 幼児の養護についての実態を調査し、養護と教育のバイブルブックを作成する
- 具体的な課題に沿った取り組み内容を実施。主には現場での対人問題。技術と意識の両面からアプローチを行う
令和二年度 事業計画
- 『養護』について継続して話し合いの場を持っていく
- マニュアルの整備を行う
- プロジェクト保育、環境について継続して探究を行う
- 教育・保育の見える化について継続して探究を行う
- Tomorrow Challenge(内部評価事業)の実施
質の向上委員会(介護・支援) IMPROVE QUALITY


経営方針
■自分の能力を精一杯使い、子ども・高齢者・障害者、保護者の方々にお返しをしよう |
■受容的環境を確立し、ご利用いただいているすべての方が「自分らしく主体として生きること」ができるサービスを提供する真のプロを目指そう |
|---|
経営目標(中・長期ビジョン)
20.受容的環境の確立 |
人的、物的両面において受容的環境を確立します |
|---|---|
21.「自分らしく主体として生きること」を目指す保育・介護・障害福祉サービスの提供 |
「真のプロ」を目標とします |
22.「将来」へつなぐ保育・介護・障害福祉サービスの提供 |
きめ細やかに個別のニーズに対応し、アフターケアの充実を図ります |
委員長の言葉
ご利用者様の人権を尊重し、個人の尊厳を守ることの重要性について職員が認識を深められるよう人権擁護や虐待防止などの人権教育や認知症の理解に向けた取り組みに力を注いでいます。「自分らしく主体として生きること」をご利用者様一人ひとりが実現できることを目指し、事例共有やケーススタディーを通して日々の介護・支援の振り返りや実践を積み重ねていきます。
委員長 樋口 宏美
令和五年度 事業計画
- 人権教育について年1回以上委員会から取り組みの発信・啓発を行う(介護・障害)
令和四年度 事業計画
- 技術標準書を各施設で作成していく
- 現場での課題を委員会で検討し、現場にバックする
令和三年度 事業計画
- 法人内で共有できるマニュアルと、各施設に特化したマニュアルを把握する
- 共有できるマニュアルを各施設で分担し、見直しを行う
令和二年度 事業計画
- 技術の向上
- 知識の向上
- 社会への発信
地域貢献委員会 REGIONAL CONTRIBUTION

経営方針
■地域課題を把握し、多様なニーズに対応できる「福祉の総合的な拠点」になろう |
■地域の「強み」「弱み」を把握し、多様なニーズに対応できる「福祉の総合的な拠点」を目標とし、さらに機能性を発揮して新しい保育・介護・障害福祉サービスを開発・提供していこう |
|---|
経営目標(中・長期ビジョン)
23.連携によるニーズの把握とスキルの獲得 |
コミュニティソーシャルワーク(CSW)の実践のためのスキルの獲得と地域のニーズを把握します |
|---|---|
24.地域課題(ニーズ)への対応 |
地域の多様なニーズに対応し、「福祉の総合的な拠点」を目標とします |
25.施設主義から機能主義へ |
機能性を発揮し、ニーズに応える新しい保育・介護・障害福祉サービスを開発・提供します |
委員長の言葉
地域貢献委員会では、日頃からの挨拶や何気ない会話を大切にしつつ、今地域社会で求められていること(ニーズ)や取り組むべき課題を一緒に考えていきます。また、地域貢献活動を他法人と連携しながらすすめていくために「ほっとかへんネット」への積極的な参画、「認定就労訓練事業」の展開をし、行政と連携をとりながら一般就労に向けて一歩を踏み出そうとしている方への支援をしていきます。
多様な委員会活動を通して、地域の皆様にとって必要とされる存在、なくてはならない存在をめざしていきます。
委員長 樋口 勲
令和五年度 事業計画
- 地域主体の行事や会議体への参加、地域貢献活動の企画、開催(各事業所で年間4回以上実施)
- 「認定就労訓練事業」の利用者の受入や学習支援、子どもや地域の居場所づくり事業の展開(各事業所で年間2回以上実施)
- CSWP(コミュニティソーシャルワークポイント)の記録(各委員もしくは事業所より年間3例以上記録)
令和四年度 事業計画
- 認定就労訓練事業の受け入れを行っていく
- ほっとかへんネットの活動に積極的に参画していく
- 地域ニーズ把握と対応のためにポイントをまとめていく
令和三年度 事業計画
- ほっとかへんネットの活動に参加し、役員法人や行政、社協とのつながりを大切にしながらオンラインを含め、できる活動の活性化をすすめる
- 「認定就労訓練事業」を立ち上げ、各事業所で受け入れを行い、地域の生活困窮者や低所得者に対しての支援につなげる
- 地域、住民が抱える課題を把握し、法人としてできる取り組みを行い、それらのポイントをまとめていく
令和二年度 事業計画
- CSWの実践、スキルの獲得
- 社会福祉法人連絡協議会「ほっとかへんネット」への参画
- 施設の開放や相談機能の拡充
共生社会の創造委員会 SYMBIOTIC SOCIETY

あなたがいるだけで、周りは笑顔

高齢者の方の力をお借りして
経営方針
■共生社会の構築と福祉教育の推進をしよう |
■「幼と老の共生」、「幼と障がい者(児)との共生」を実践し、その価値観を広め、共生社会の構築を図るとともに、それを支える福祉文化の確立のため、福祉教育を推進しよう |
|---|
経営目標(中・長期ビジョン)
26.幼老障共生社会の再構築 |
幼老障共生の環境づくりを進め、互いに支えあう共生社会の再構築を図ります |
|---|---|
27.福祉教育の推進 |
地域の幸福を願い、共生社会の構築のため、福祉教育を推進しますケア、サービスに対する積極性を失わぬよう留意し、怪我、事故をなくします |
委員長の言葉
みかり会では長年、異年齢や、異世代、支援が必要な方など、“多様な関わり”が持つその価値を実践しながら探求してきました。今年度も具体的な取り組みとして、それぞれが別々ではなく一緒に生活することで、多様性(ダイバ―シティー)を自然と受け入れながら互いに認め合い、誰もが自分らしくいられる共生社会の創造の実現を目指します。
また、その「価値」を保護者の皆様方や地域の方々と考える機会を持ち、社会にも積極的に発信させていただくことで、微力ではありますが、世の中にお返しをしていきたいと考えています。
委員長 永井 安希子
令和五年度 事業計画
- インスタグラムを用いて定期的に共生社会の実践を発信していく(年間6回)
- 学校で使えそうな福祉の仕事に関する子供向けの資料を作成する(小学校向け一部、中学校向け一部)
- 施設から、機会をとらまえて地域に発信していく(年間5回)
令和四年度 事業計画
- 高齢者の社会参加に関する制度の把握・理解を促すための周知会議を行う(年2回)
- HP更新の仕組みを構築して、更新を行う(年1回)
- 障害者に特化したモニタリング調査の実施を行う(年6事例)
令和三年度 事業計画
- 幼老共生の動画作成を行い、法人の強みを発信する
- 幼障共生の動画作成を行い、法人の強みを発信する
- 法人内研修での実践事例の発表
令和二年度 事業計画
- 幼老障共生の効果・数値についての研究
- 「見える化」の資料を用いて社会への発信
- 「見える化」の資料で園内研修の実施
リスクマネジメント委員会 RISK MANAGEMENT

消防署との連携

地震訓練の風景 大人も子どもも真剣に
経営方針
■安全性を高め、安心して頼られる存在になろう |
■怪我・事故、人格権侵害、財産権侵害、風評被害、経済的被害などのあらゆる危害に備えるため、リスクマネージメントを実践し、地域の中で安心して頼られる存在になろう |
|---|
経営目標(中・長期ビジョン)
28.予防(発生確率の低減)する |
想定外をなくし、システムを整備、周知を図り、事故等の発生確率の低減を図ります |
|---|---|
29.被害規模(ダメージ)を小さくする |
好感をもたれる組織風土の確立と事前の準備・訓練を行い、あらかじめ被害規模を小さくできるように努めます |
30.クライシスマネジメント |
発生後の的確な対処方法を整備します |
31.人格権侵害をなくす(人権の尊重) |
人権の尊重や、個人の尊厳に配慮した良質な保育・介護・障害福祉サービスの提供に努めます |
32.個人情報の保護 |
プライバシー、個人情報の保護に努め、信頼性の高い保育・介護・障害福祉サービスを提供します |
33.経済的被害に備える |
経済的な基盤を整え、事業の継続性を高めます |
委員長の言葉
当法人に関わる全ての方の「安全性の確保」「安心」を確立し、「信頼」へと繋いでいきたいと考えております。リスク(危機)に対する事前の備えを盤石にし、事後の被害を最小限に留めることができるようにマネジメント(管理)していきます。
委員長 高崎 祐太
令和五年度 事業計画
- 中堅以上の職員を対象にブラインド型ロールプレイ訓練を行う(各施設年間1回)
- 在宅ワークにおける個人情報の適切な管理についての指針を作成する(年間1回)
- 節電強化月間と並行して更なる取り組みを模索する(年間1回)
令和四年度 事業計画
- 各施設で自然災害BCP、感染症BCPに沿った訓練を行う
- コスト意識の情勢の為の取り組み強化月間を作成し、リスク委員を中心に発信していく
令和三年度 事業計画
- BCM・BCPが機能するか訓練を実施する
令和二年度 事業計画
- 事業継続計画(BCP)の完成
- 風評被害への対策整備
- 計画的な訓練実施と評価、改善